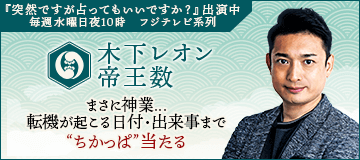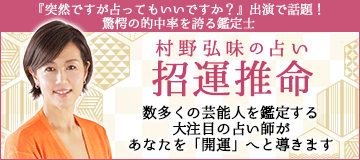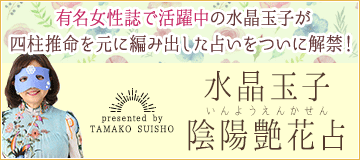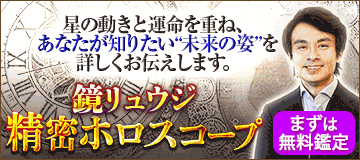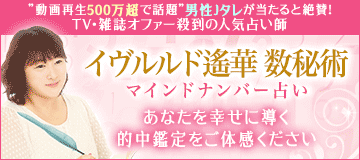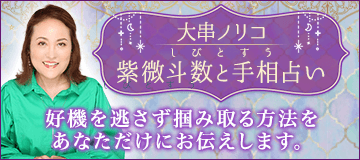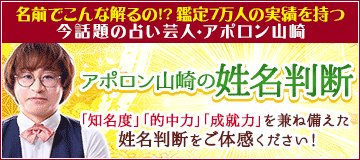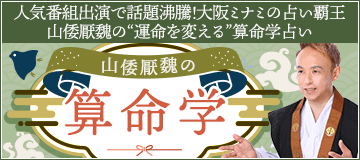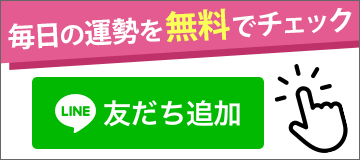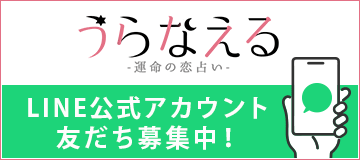立秋(りっしゅう)とは?
立秋とは、二十四節気の1つで、秋の始まりの時候を表す13番目の二十四節気です。
時期としては8月初旬のため、まだまだ夏真っ盛りの暑い時期ですが、昔の暦の上では秋にあたります。
日中は暑さが厳しく、1年で最も気温が高い日もありますが、それも立秋の日を境として徐々に落ち着いていき、朝夕には涼しい風を感じるようになります。
まだまだ暑いのに、この時期から秋になるのは、そもそも二十四節気が古代中国時代に寒い気候の土地を基準に作られたからと言われています。気候の変化があるとはいえ、この時期には秋らしさを感じられていたと思われます。

2025年の立秋はいつ?
2025年の立秋は、2025年8月7日(木)です。
目次
二十四節気(にじゅうしせっき)とは?

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、紀元前の中国で太陽暦を使用していた時代に、季節を表すものとして太陽の動きに基づいて誕生した概念です。
1年を「春・夏・秋・冬」の4つの季節に分類し、さらにそれぞれの季節を6つに分け、合計24等分したものに名称をつけたものです。それゆえ、二十四節気と名付けられました。ちなみに、「節」は中国語で「区切り」の意味があります。
四季の始まりを表す「立春」「立夏」「立秋」「立冬」は二十四節気の「四立(しりゅう)」と呼ばれます。
また1年で最も日が短い「冬至」、1年で最も日が長い「夏至」、昼と夜の長さが同じ日を「春分」「秋分」と呼ばれ、この4つは「四至(しし)」と呼ばれます。
二十四節気は1年の変化の法則を定めたものとして、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。
立秋の第三十七候、第三十八候、第三十九候とは?
二十四節には四季よりもより細やかに季節の移ろいを表す七十二候があります。
二十四節の1節をさらに約5日ごとに3等分し、1年を七十二に分けたもので、立秋には第三十七候、第三十八候、第三十九候があります。
第三十七候は、8月7日から8月11日頃で「涼風至(すずかぜいたる)」時期と呼びます。字の通り、早朝や夕暮れには涼しい風を感じられるようになる時期を指します。
第三十八候は、8月12日から8月16日頃で「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」時期と呼びます。ひぐらしが甲高く鳴く頃を表した時期を指します。
第三十九候は、8月17日から8月22日頃で「蒙霧升降(ふかききりまとう)」時期と呼びます。蒙霧とは、濃い霧を指します。厳しい残暑は残っているものの、朝夕には涼しい風が吹き、湿り気を帯びた空気が白い霧に変わる時期を指します。
立秋と「暑中お見舞い」「残暑お見舞い」について
立秋に入ると、暦は秋になりますので、季節の挨拶も「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」に変わります。
秋なのに「残暑」とつくのは、秋に入ったとはいえ、まだまだ暑さの厳しい日が続いているためです。
立秋を境に、口語でも「暑さが厳しいですね」よりも「残暑が厳しいですね」といったほうが、季節が感じられ、年配の方には喜ばれるかもしれません。
ちなみに、暑中見舞いを出すのは小暑(7月7日頃)から立秋の前日(8月7日頃)までですが、残暑見舞いは字の通り暑さが残っている時期であればいつでも使えるので、いつまでという期限はありません。
ただ一般的には8月末頃までとしている人が多いようです。
立秋の行事や風習とは?

日本の一部の地域では7月にお盆とするところもありますが、一般的には立秋の期間である8月13日から8月16日にお盆を迎えます。
この時期には親族のお墓参りに行ったり、仏教では先祖の霊が家に帰ってくる時期と言われているため祖先の霊を家にお迎えしたりと、宗教的な行事が多く行われます。
また、お迎えをした祖先の霊を供養して再び送り出す儀式として始まった、お盆祭りもこの時期に全国各地で催されます。
ちなみに、お盆祭りで踊る盆踊りは死者を供養したり、精霊を迎えたりするための念仏踊りが民間習俗と交わって形を変えたものだとされています。
立秋の旬の食べ物とは?
立秋の旬の食べ物といえば、暑気払いができる涼しいものです。
それは夏の果物の代表である、スイカです。
スイカはアフリカ原産ですが、そこから中国の西方にあるウイグルから中国に伝わり、日本ヘは室町時代頃に渡来しました。スイカを漢字で西瓜と書くのは、中国の西方から伝わってきた瓜のような食べ物であるからとのこと。
実は西瓜は夏ではなく秋の季語で、本来は初秋に食べるものだったそうです。水分と糖分が含まれたスイカは、厳しい暑さが残る時期の良い熱中症予防になります。
立秋の旬の花や植物とは?

立秋に見頃を迎えるのは、ひまわりです。
ひまわりは英語でSunflower、中国語で太陽花と呼ばれ、どこの地域でも太陽と結びつきがあり、人々に明るいイメージを持たれている親しみ深い花です。背の高いひまわりが立ち並ぶひまわり畑が各地で見られ、その姿は圧巻です。
他にも、鮮やかな青い花を咲かせる露草や、開花してから白からピンクへと変化する可愛らしい花を咲かせる月見草も旬を迎えます。露草は朝に咲くのに対し、月見草はその名のごとく夜に開花する植物です。
立秋の過ごし方とは?
立秋は暦の上ではもう秋ですが、気温的には立秋の前の時候である大暑とあまり差異がありません。
だんだんと朝夕に涼しい風が吹くようになって秋めいてくるとはいえ、まだまだ熱中症対策を怠らず、暑気払いをしながら健康的に過ごすよう心がけましょう。
また、立秋にはお盆を迎えます。
お墓参りや祖先の霊を迎えるなど、全国各地で生活している親族が一堂に会する機会です。お盆には帰省をして、改めて家族の絆やふるさとの大切さを再確認してみてはいかがでしょうか。
なかなか会えない遠方にお住まいの親族やお世話になった方々には、残暑見舞いを出すと喜ばれます。

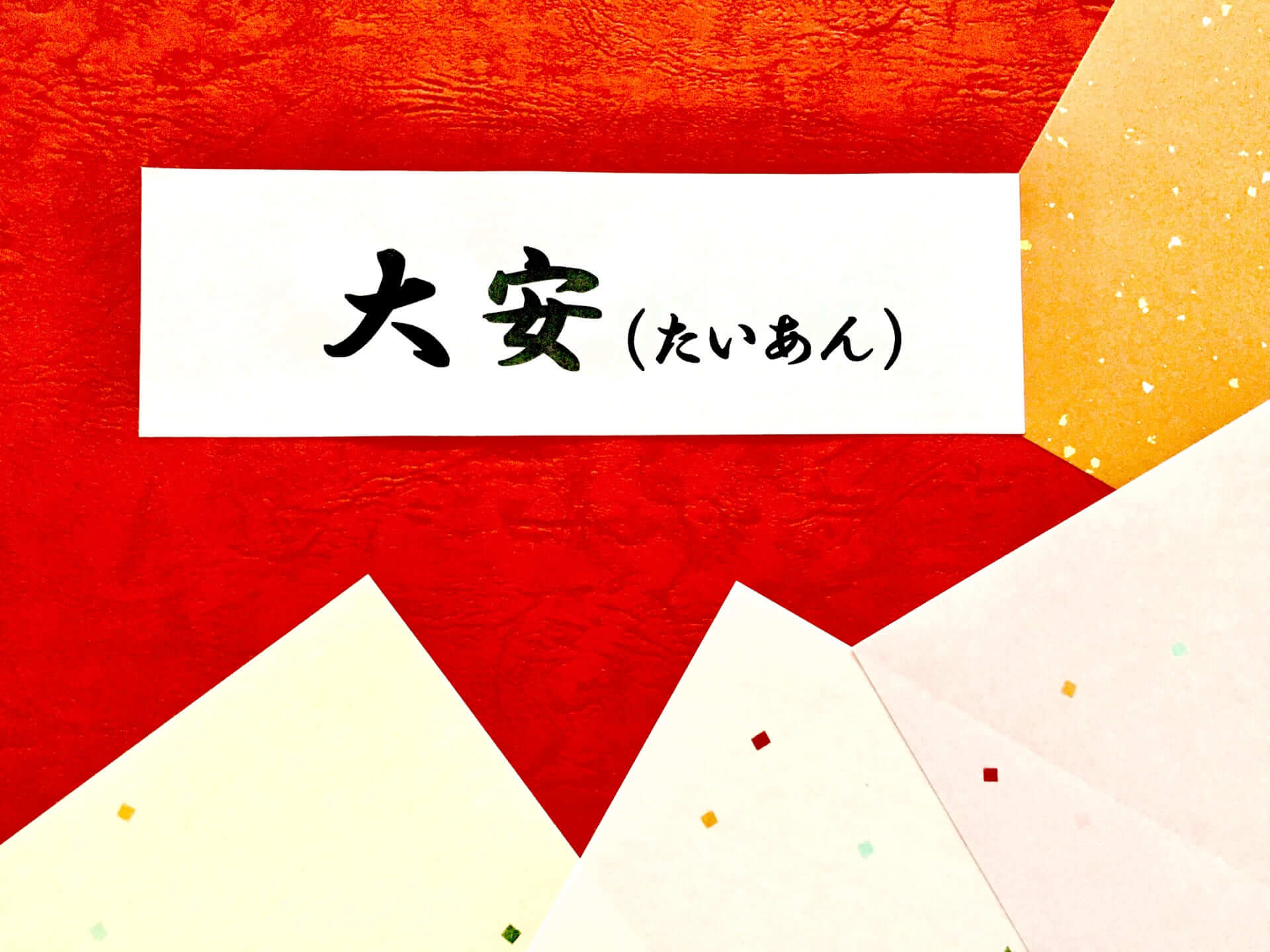
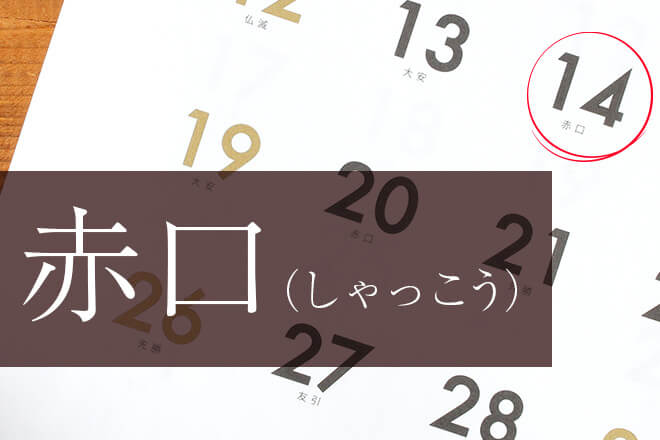





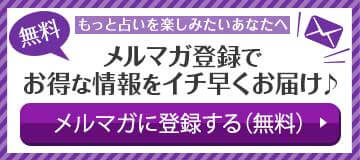
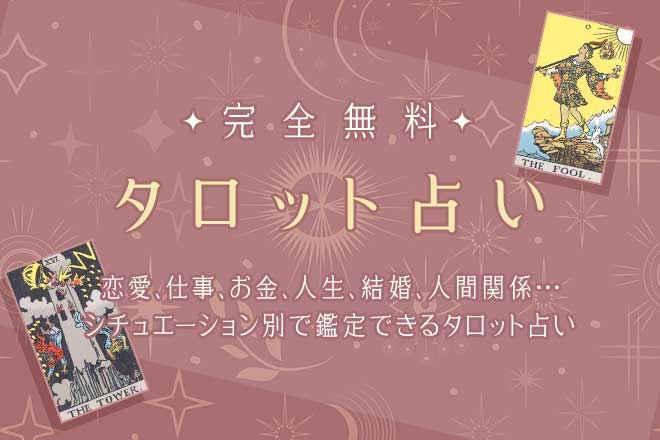




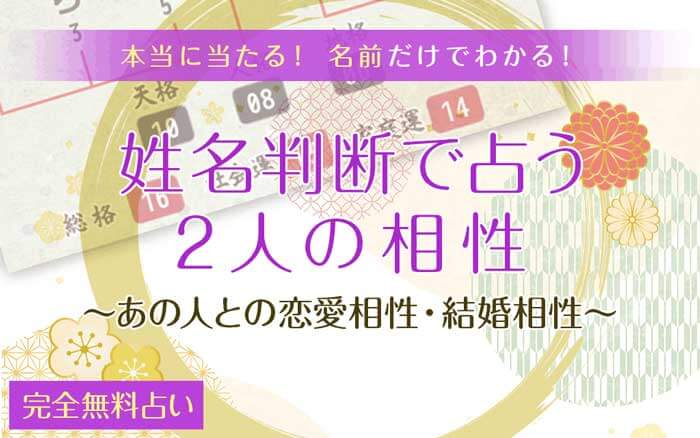
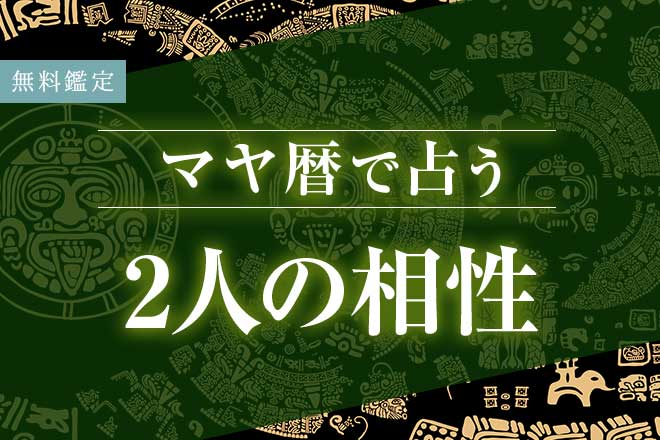
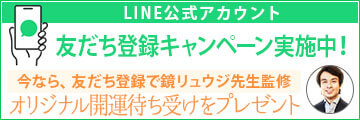






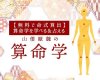
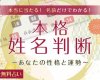
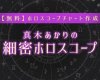













 Keikoの恋占い◆あの人の本心は何?
Keikoの恋占い◆あの人の本心は何?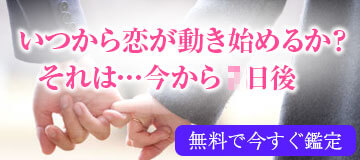 Love Me Doの恋占い。あの人があなたに抱く想い
Love Me Doの恋占い。あの人があなたに抱く想い