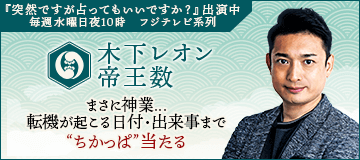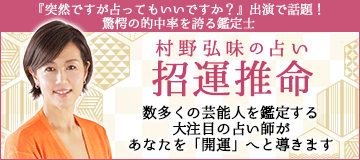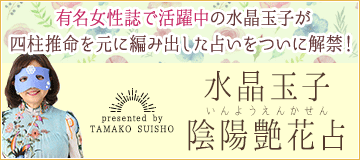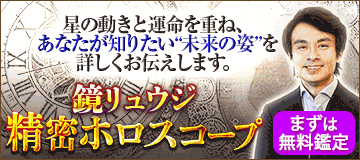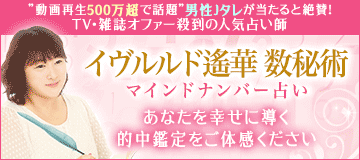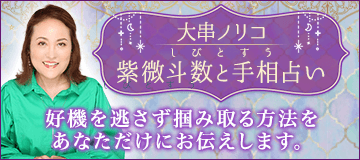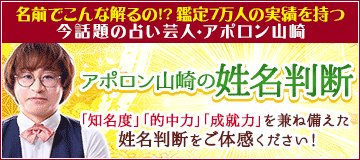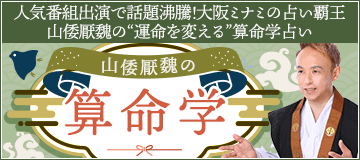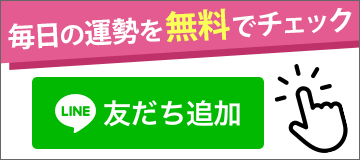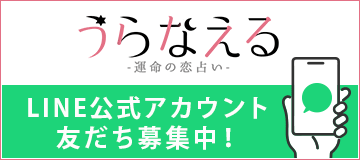大暑(たいしょ)とは?
大暑とは、二十四節気の1つで、厳しい暑さが感じられる夏本番の時候を表す12番目の二十四節気です。
大暑は梅雨明けの時節で、眩しいほどに照り返す日差しと青空、そして入道雲が浮かぶ、夏らしい景色が広がります。蝉の声が響き渡り、トンボも飛び交い始めます。
梅雨の終わりとともに雷や夕立も多く「大暑」と書く通り、次第に真夏に向けて気温も上昇していきます。
特に梅雨明け後の10日間は「梅雨明け十日」と呼ばれ、1年で最も暑い時期とされています。
現代から見るとまだまだ夏本番の序章といった時節ですが、暦の上では夏の最後の節気となり、大暑が過ぎると立秋となり、早くも秋を迎えます。

2025年の大暑はいつ?
2025年の大暑は、2025年7月22日(火)です。
目次
二十四節気(にじゅうしせっき)とは?

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、紀元前の中国で太陽暦を使用していた時代に、季節を表すものとして太陽の動きに基づいて誕生した概念です。
1年を「春・夏・秋・冬」の4つの季節に分類し、さらにそれぞれの季節を6つに分け、合計24等分したものに名称をつけたものです。それゆえ、二十四節気と名付けられました。ちなみに、「節」は中国語で「区切り」の意味があります。
四季の始まりを表す「立春」「立夏」「立秋」「立冬」は二十四節気の「四立(しりゅう)」と呼ばれます。
また1年で最も日が短い「冬至」、1年で最も日が長い「夏至」、昼と夜の長さが同じ日を「春分」「秋分」と呼ばれ、この4つは「四至(しし)」と呼ばれます。
二十四節気は1年の変化の法則を定めたものとして、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。
大暑の第三十四候、第三十五候、第三十六候とは?
二十四節には四季よりもより細やかに季節の移ろいを表す七十二候があります。
二十四節の1節をさらに約5日ごとに3等分し、1年を七十二に分けたもので、大暑には第三十四候、第三十五候、第三十六候があります。
第三十四候は7月22日から7月27日頃で「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」時期と呼びます。初夏の花である桐が盛夏を迎え、実を結び始める時期を指します。
第三十五候は7月28日から8月1日頃で「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」と呼びます。字の通り、真夏の熱気を受け土が蒸す時期を指します。ちなみに「溽暑」はじっくりと蒸し暑い様を表す単語です。
第三十六候は8月2日から8月6日頃で「大雨時行(たいうときどきふる)」時期と呼びます。夏の雲である入道雲が発達し、集中豪雨や夕立が増える時期を指します。
大暑と「土用の丑の日」の関係
夏の土用に巡ってくる「丑の日」のことを『土用の丑の日』と言います。この日は、現代ではうなぎを食べる日とされています。
土用は、中国古くから伝わる五行説「木火土金水」を四季に当てはめたもので、立春・立夏・立秋・立冬前の約18日間を指します。
夏の土用の丑の日は大暑に巡ってくるため、この時期に精のつくうなぎを食べて暑さの厳しい時期を乗り越えてきました。
うなぎの他にも、丑の「う」のつく食べ物として、梅干し、うどん、瓜などを食べて滋養強壮に役立ててきました。
その中でもうなぎが有名なのは、江戸時代の蘭学者・平賀源内が売り上げに悩んでいたうなぎ屋にアドバイスをしてうなぎブームが広がったという説があります。
大暑の行事や風習とは?

大暑では全国各地で花火大会や夏祭りなどが催され、1年で最も賑やかな時期といえます。
なかでも大暑のお祭りとして有名なのが、青森のねぶた祭です。
ねぶた祭は東北を代表する夏祭りで、奈良時代に中国から伝来した「七夕の灯篭流し」が起源とも言われており、そこから忙しい夏の農作業の妨げとなる怠け心や眠気を流す「眠り流し」に発展しました。
この「眠り流し」が「ねむたながし」、「ねむた」、「ねぷた」と訛り、「ねぶた」となったと言われています。
現代では武士や神話などの1シーンをモチーフにした大迫力の山車が街中を練り歩き、厳しい夏に打ち勝つ活力を人々に与えています。
大暑の旬の食べ物とは?
大暑に旬を迎える食材は、沖縄料理で有名なゴーヤや、瑞々しく夏の暑い時期にも食べやすいとうがん、ぶどう、なす、オクラ、ししとうがらし、とうもろこしなどが挙げられます。
ちなみに、旧暦の8月1日を指す八朔は、みかんに似た柑橘類の1つですが、本来は8月1日に行っていた豊穣祈願のことを指し、大暑の時期の八朔はまだ身が小さく食べ頃ではありません。
食べ物というとアイスクリームなど氷菓子がよく売られている季節になります。実はかき氷の歴史は古く、平安時代の女流作家・清少納言が夏にかき氷を食べていたという記述を残しています。
大暑の旬の花や植物とは?

大暑の旬の花や植物と聞いて、真っ先にひまわりを連想する人は多いのではないでしょうか。
ひまわりは、実は日本の固有種ではなく、北アメリカ原産のキク科の一年草で、江戸時代に日本に渡来しました。当初は「丈菊(じょうぎく)」や「日輪草(にちりんそう)」と呼ばれていました。
他にも、夏の代名詞ともいえる朝顔や、夕方から翌日の午前中にかけて開花する白粉花(おしろいばな)、秋の七草にも数えられる女郎花(おみなえし)が見頃を迎えます。
大暑の過ごし方とは?
大暑になると梅雨が終わり、1年で最も暑い日差しの厳しい時期を迎えます。
日本では古来よりこの暑さを乗り越えるため、氷菓子やそうめん、瑞々しいとうがんやぶどう、またはうなぎや梅干しなどの精のつく食べ物を食べて滋養強壮としました。
さらに、水遊びや酒盛り、花火や夏祭りなどをして、うまく暑気払いをして日々を過ごしてきました。
現代では涼しい室内で快適に過ごせますが、屋内でじっとしているだけでは体がなまり、逆に夏バテに繋がってしまう可能性があります。
日中は風鈴やすだれ、金魚鉢などの伝統的な夏の涼を取り入れて暑さをやわらげたり、気温が下がる夕刻に夏祭りや花火大会に出かけたりして、暑いからこそ積極的に体を動かして夏の思い出を作ってみてくださいね。

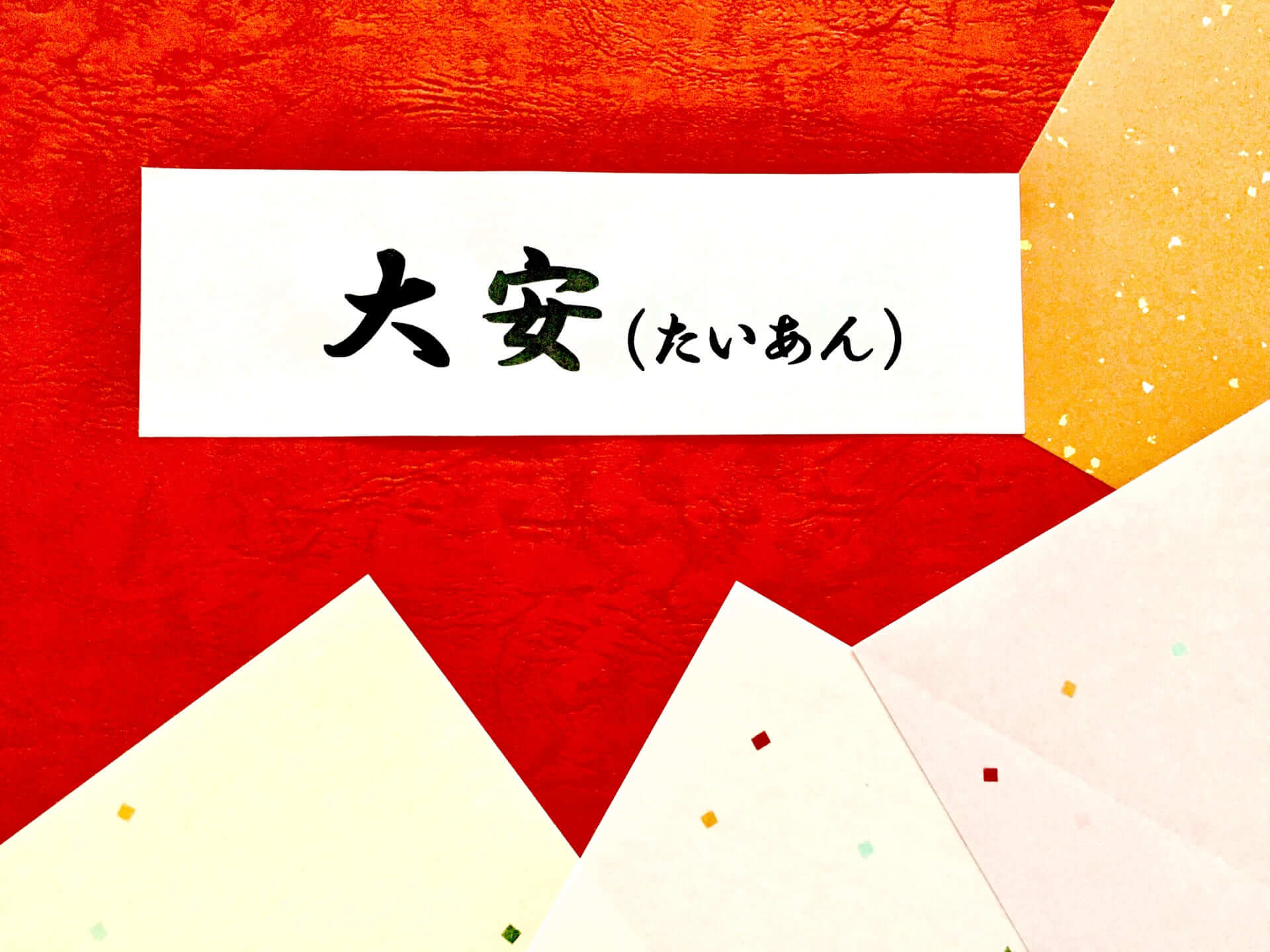
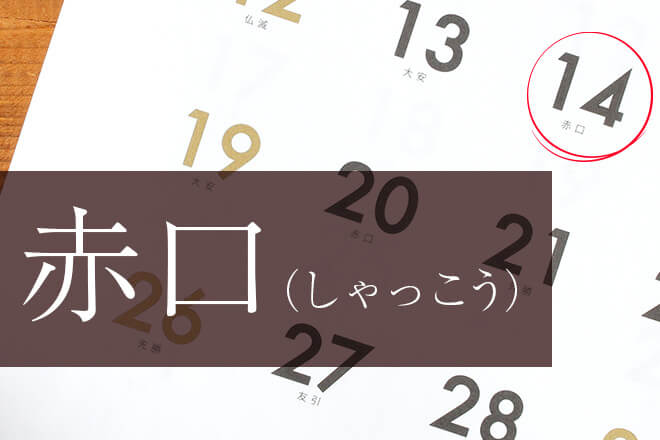





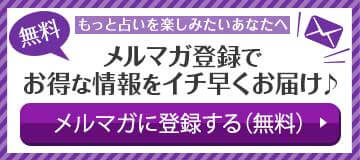
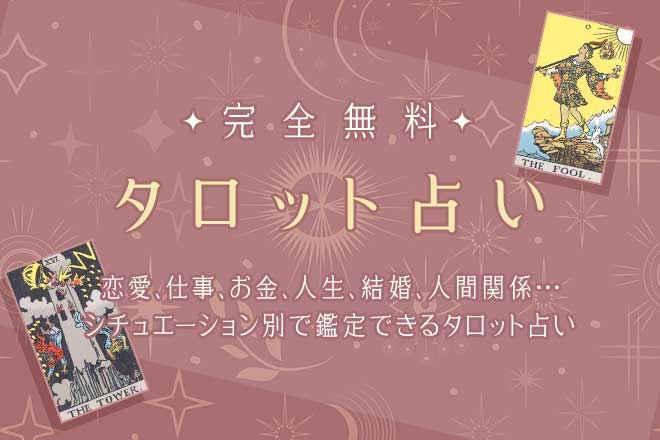




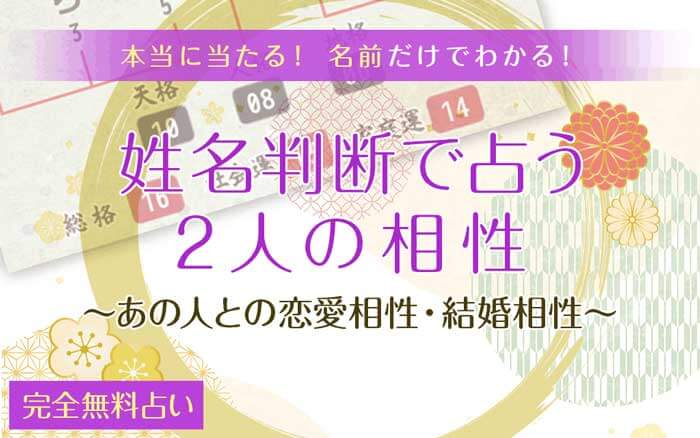
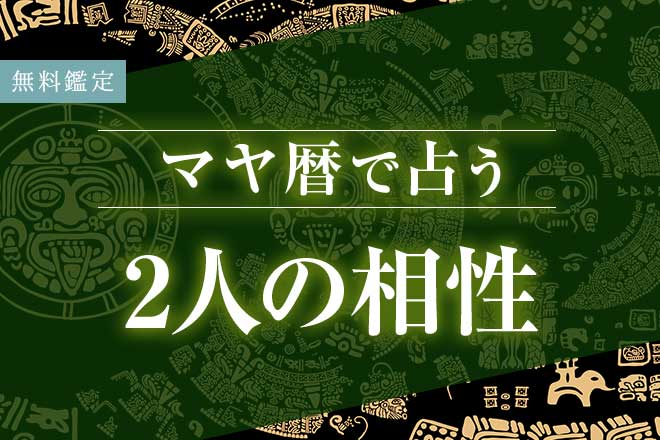
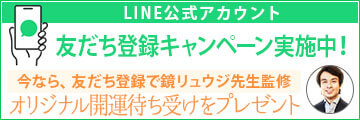






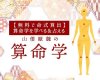
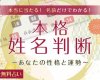
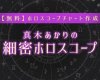













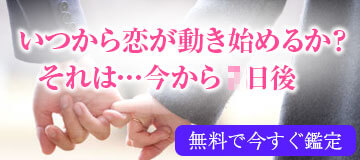 Love Me Doの恋占い。あの人があなたに抱く想い
Love Me Doの恋占い。あの人があなたに抱く想い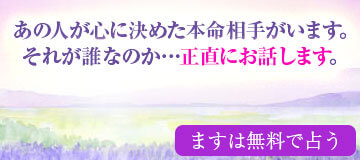 水晶玉子が占う、2人の本当の恋相性
水晶玉子が占う、2人の本当の恋相性